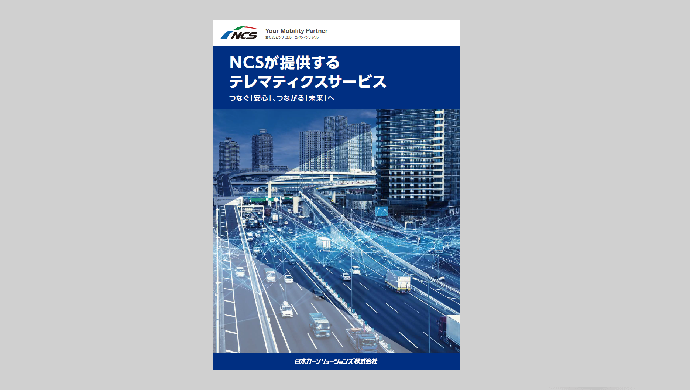「安全運転義務違反」とは?企業が知るべきリスクと対策の基本

社用車の事故削減は多くの企業が抱えている課題ではないでしょうか。交通事故原因の約7割を占める「安全運転義務違反」は、企業の安全配慮義務にも関わる重要課題です。しかし、安全運転の指導効果が見えにくいと感じる担当者も多いでしょう。本記事では違反の基本から、データ活用で実現する効果的な安全運転管理のヒントまでを解説します。
「安全運転義務違反」とは?

「安全運転義務違反」という言葉は、自動車を運転する方なら一度は耳にしたことがあるでしょう。安全運転義務は、単に個人のドライバーが注意して運転するというものではなく、企業の車両管理や安全運転管理者にとって、常に意識し、対策を講じるべき重要なテーマです。本稿では、この「安全運転義務違反」の基本から、企業が直面するリスク、そして具体的な予防策までを解説します。
道路交通法第70条で定められた義務違反
「安全運転義務」は、道路交通法第70条で以下のように明確に定められています。
- 道路交通法第70条
- 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない
これは、すべてのドライバーに課せられた注意義務の基本であり、自動車を運転する上で最も重要なルールのひとつです。この義務を怠り、結果として事故や交通の危険を引き起こした際に適用されるのが「安全運転義務違反」です。運転マナーの向上だけでなく、交通事故防止の観点からも、この条文の理解は不可欠といえるでしょう。
抽象的だからこそ管理が難しい
「安全運転義務」は、「他人に危害を及ぼさないような速度と方法」と抽象的な表現で規定されています。「〇km/hオーバー」の速度超過や信号無視のように明確な数値基準がないため、何が違反にあたるかを判断しづらいのが実情です。
このため、安全運転管理者によるドライバー指導は「気を付けて運転するように」といった個人の感覚に頼った漠然としたものになってしまいます。これでは指導内容にばらつきが生じ、企業のリスク管理として体系的な運転管理を行う上で大きな課題となります。
どんな運転が「違反」になるのか?
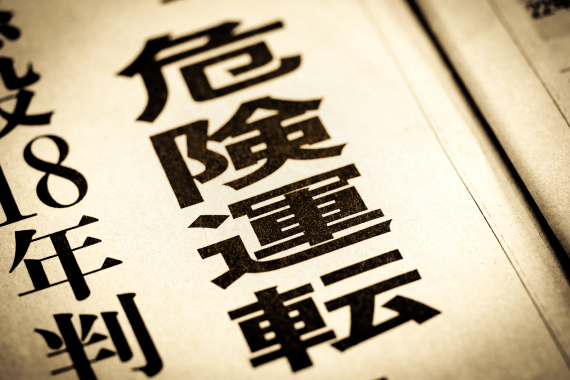
抽象的でわかりにくい「安全運転義務違反」ですが、実際の交通事故統計を見ると、その実態が明らかになります。内閣府の資料によると、令和6年度の事故原因の半数以上がこの違反によるものとされています。
特に「漫然運転」や、近年問題となっている「スマホ運転」などは、重大事故に直結する危険運転です。本章では、具体的にどのような運転が違反に該当するのか、その区分と違反事例を解説します。
6つの違反区分
警察庁の交通事故統計において、安全運転義務違反は主に以下の6つに分類されます。自社のドライバーがどのような状況に陥りやすいか把握することが、リスク管理の第一歩です。
運転操作不適
ハンドル操作の誤り、ブレーキとアクセルの踏み間違いなどが該当します。特に不慣れな社用車の運転時や、駐車時などに起こりやすい違反事例です。
漫然運転
疲労の蓄積や考え事などにより、運転への集中力が低下した「ぼんやり運転」状態を指します。危険の発見が遅れ、重大な事故につながる過失責任を問われるケースも少なくありません。
脇見運転
近年特に問題視されているスマホ操作の「ながら運転」やカーナビの注視などが典型例です。わずか数秒でも車両は数十メートル進むため、極めて危険な運転と言えます。
動静不注視
歩行者や他の車両の存在は認識しつつも、「相手が止まるだろう」といった自分に都合の良い判断をしてしまうことです。交差点での右左折時によく見られる違反事例です。
安全不確認
交差点進入時の一時停止後に行う左右確認、バック時の後方確認、車線変更時の目視確認などを怠ることです。「見ているつもり」がヒヤリハットや事故の原因になります。
安全速度
法定速度内であっても、見通しの悪い交差点やカーブ、悪天候時など、道路や交通の状況に応じて適切に減速しなかった場合に適用されます。
その他(予測不適)
上記のいずれにも分類されない、その他の安全運転義務違反です。
その中でも特に注意したいのが「予測不適」です。これは相手が減速してくれるだろう、前方車との車間は十分だろうといった思い込みや、自分の運転感覚の誤りが原因となるケースを指します。
事故の発生原因ではトップクラス
安全運転義務違反が、いかに交通事故の主要な原因であるかは、警察庁の統計データが明確に示しています。同庁が公表した「令和6年中の交通事故の発生状況」によると、年間の交通事故総数268,704件のうち、安全運転義務違反が原因とされるものは185,516件にものぼります。これは事故全体の69.0%を占めるという極めて高い割合です。
参考:令和6年中の交通事故の発生状況|警察庁統計
この数字は、多くの交通事故がドライバーの注意義務の欠如、つまり「漫然運転」や「脇見運転」といった少しの不注意により引き起こされている実態を浮き彫りにします。企業にとって、安全運転義務違反への対策を講じることが、効果的な交通事故防止とリスク管理の鍵を握っているといえるでしょう。
違反すると何が起こる?企業としてのリスクも

安全運転義務違反が発覚した場合、まずドライバーには違反点数や反則金といった行政処分が科されます。しかし、リスクはそれだけにとどまりません。社用車が事故を起こした場合、ドライバー個人の過失責任だけでなく、企業としての管理体制が問われることになります。
人身事故になると「安全配慮義務違反」として多額の損害賠償を請求される可能性もあります。本章では、違反がもたらすドライバー個人への罰則と、企業が直面する経営上の重大なリスクについて詳しく解説します。
ドライバーには違反点数と罰則
安全運転義務違反を犯したドライバーには、行政処分として罰則が科せられます。事故に至らなかった場合でも違反が確認されると、基礎点数として2点が加算され、車種に応じた反則金を納付しなければなりません。この反則金を納付しない場合は刑事手続きへ移行し、懲役刑や罰金刑となる可能性があります。
さらに重大なのが、人身事故を起こした場合です。このケースでは基礎点数に加え、被害者の負傷の程度や運転者の過失責任の度合いに応じて、2点から最大20点の付加点数が上乗せされます。たった一度の違反が、免許停止や取消しといった深刻な結果を招くこともあるのです。
企業は「安全配慮義務違反」が問われる場合も
従業員が社用車で事故を起こした場合、その責任はドライバー個人にとどまりません。企業には、従業員の安全と健康を守る「安全配慮義務」があります。もし、企業が必要な安全運転教育やドライバー指導を怠っていたと判断されれば、この義務に違反したとして、使用者責任(民法第715条)等に基づき、被害者への損害賠償責任を負う可能性があります。
企業事故は、多額の賠償金だけでなく、社会的信用の失墜という重大な経営リスクに直結するでしょう。企業コンプライアンスの観点からも、日頃から安全運転の管理体制への注力は不可欠です。
違反を防ぐには?安全運転対策の基本と実践例

安全運転義務違反がもたらすリスクを回避するためには、ドライバー個人の意識に任せるだけでは不十分です。本章では、企業として取り組むべき「安全運転教育」の徹底、実効性のある「社内ルールと管理体制の強化」について解説します。さらに、多くの企業が抱える「なぜ安全運転教育の効果が出ないのか」という課題にも踏み込み、効果的な予防教育のヒントを探ります。
安全運転教育の徹底
交通事故防止の根幹をなすのが、継続的な安全運転教育です。ドライバーの知識や運転マナーを向上させるためには、さまざまな運転研修の組み合わせが求められます。基本的な道路交通法の知識を学ぶ座学や、時間と場所を選ばずに学習できるeラーニングは導入を検討している企業も多いでしょう。
加えて、実際の事故映像やヒヤリハット事例の動画の視聴は、危険を疑似体験できるため意識向上を促します。また、一方的な知識の伝達だけでなく、グループ討議などでドライバー自身が危険について考える参加型の予防教育も効果的なドライバー指導のポイントです。
社内ルールと管理体制の強化
安全運転教育の効果を定着させるには、具体的な社内ルールとそれを運用する管理体制の強化が欠かせません。まず、法律上の義務として、「乗車定員11人以上の自動車を1台以上」または「その他の自動車を5台以上」使用する事業所では安全運転管理者の選任が必須です。
安全運転管理者は、運行管理の中核として、車両の日常点検の徹底、運転前後のアルコールチェックの実施、ドライバーに「運転日報」の記録を義務化する責務を負います。運転日報は、走行記録だけでなく、ドライバー自身の安全意識を日々促すツールです。こうした制度の整備が、企業の安全配慮義務を果たす上での土台になります。
教育効果を最大化できない理由とは
安全運転教育や運転研修を定期的に実施し、管理体制を整えても、企業事故や違反がゼロにならないのが現状です。その背景には、運転管理における「見えない壁」が存在します。つまり、ドライバーの運転スキルや危険感受性には個人差があり、研修内容の理解度も人それぞれであることが理由として挙げられます。
また、安全運転管理者によるドライバー指導が、管理者本人の経験に頼った属人的なものに陥りがちで、指導の標準化が難しいことも特筆すべき点です。結局のところ、管理者は同乗しない限りドライバーが普段どのように運転しているのか、正確に把握できません。この「見えない課題」こそが、効果的な予防教育を阻む要因といえるでしょう。
NCSのテレマティクスサービスが支援できること

前章で属人的な指導による安全運転教育の限界や「見えない運転」という根本的な課題について挙げました。この課題を解決し、運転管理を次のステージへ引き上げるのが、NCSが提供する法人向けテレマティクスサービスです。
テレマティクスサービスは、車載器から得られる走行データを活用し、ドライバー個人の運転状況を客観的に「見える化」できます。そのため、勘や経験に頼らない、データに基づいたドライバー指導を可能にし、企業事故や違反の削減、ひいては企業コンプライアンスの強化につながるでしょう。
事故や違反を減らすための機能
NCSの法人向けテレマティクスサービスは、車載器を通じてドライバーの運転データをリアルタイムに収集・分析し、「見える化」します。特に、急加速・急ブレーキといった危険運転を検知し警告する機能や、運転全体を客観的に評価する「スコアリング」機能が安全運転教育に有効です。
テレマティクスサービスの機能により、これまで確認できなかった運転状況が具体的な数値やレポートとして把握可能になります。ドライバーはレポートから自身の運転の癖を自覚することで自発的な運転改善の意欲向上につなげられるでしょう。安全運転管理者は、勘や経験に頼らず、データに基づいた公平なドライバー指導が可能です。
社内評価・企業価値向上につながる
NCSのテレマティクスサービス導入効果は、事故削減だけではありません。客観的な運転スコアリングデータは、公平な人事評価の要素として活用でき、ドライバーの安全運転への意識向上につながります。
また、運転日報の自動作成機能は、管理業務の効率化にも貢献します。交通事故防止への積極的な取り組みは、自動車保険料の削減という直接的なコストメリットに加え、企業の社会的責任(CSR)やESG経営の観点からも重要です。安全への投資は、企業コンプライアンスを遵守する姿勢の表明であり、最終的に企業価値全体の向上へとつながるでしょう。
まとめ
安全運転義務違反は交通事故の最多原因であり、企業に損害賠償や社会的信用の失墜といった経営リスクをもたらします。一般的な安全運転教育だけでは、ドライバー個々の運転実態が見えず、指導が属人的になりがちです。NCSのテレマティクスは運転を「見える化」し、データに基づく公平な指導を実現。効果的な事故防止と企業価値向上に貢献します。