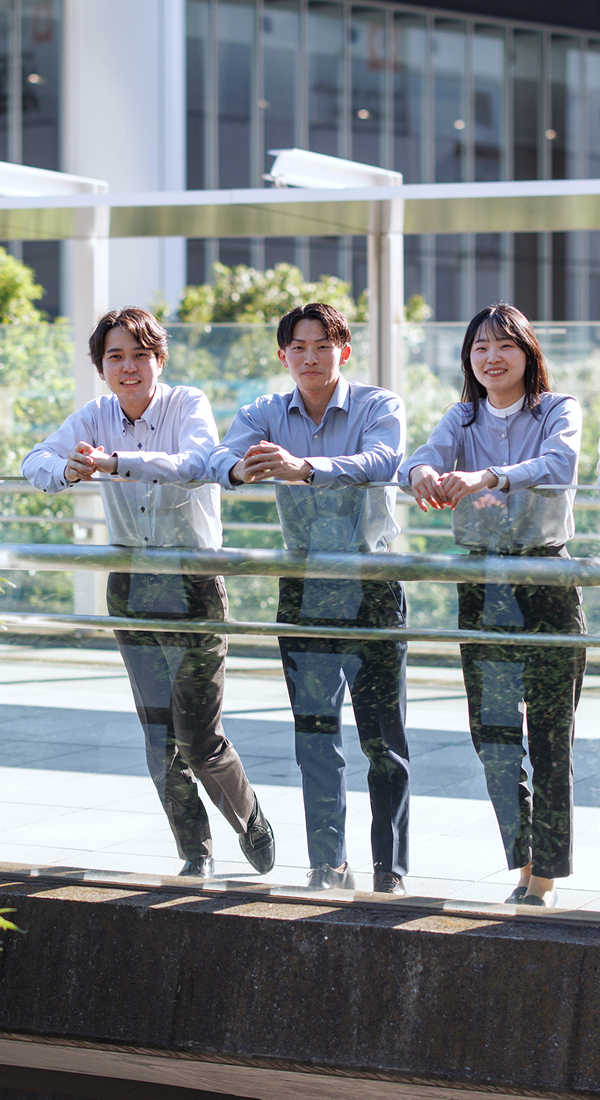プロジェクト
ストーリー
~EVリース導入プロジェクト~
社会に必要とされる電気自動車の推進。
時代を先駆け、走り抜いたチームの軌跡を紹介します。
顧客への“EVリース推進”という
新たな試みとその功績
度重なる災害に停電。電気自動車(EV)の可能性に気づいたNCSは、EVがまだ今ほど広がっていない2018年、EVのリース推進プロジェクトを立ち上げる。営業を始めた最初の3ヶ月で契約できたのは、たった10台ほど。しかし、今や、さまざまな企業から導入の相談を持ちかけられるほどにプロジェクトは成長した。苦難を乗り越えた成功の鍵はどこにあったのか。

写真左から
- 営業第二部 次長 K・M
- 営業統括部マネージャー S・T
- 東京営業部 K・R
プロジェクト成功のポイント

度重なる災害の問題解決方法を模索

BCP対策、SDGsと時代を掴む先見性

自動車メーカーをうならせた知識の収集
EVの可能性を再認識した、
北海道胆振東部地震のブラックアウト
いつ頃からEVリースのプロジェクトに着手したのでしょうか?
K・M:2016年頃に自動車業界に大きな変革を促す「CASE」というキーワードが聞かれるようになりました。英語でコネクテッド(Connected)、自動運転(Autonomous)、シェアリング(Shared)、電動化(Electric)を意味する単語の頭文字です。自動車が単に所有して乗るものではなくなってきたのです。自動車の価値そのものが変化し始めていました。この変革はオートリース会社にとってもチャンスと考えました。私たちは、まずはEVに着目し、お客さまにどうEVをプロモーションしていくか、という研究のため、2018年に本格的なEVリースの企画に着手し始めました。
北海道胆振東部地震の停電があった年ですね?
K・M:そうです。皆さんご記憶にある通り、ブラックアウト(大規模な停電)があり、その時に、現地のコンビニエンスストアの行動が注目を集めました。当時、停電が続く中、ガソリン車を使って発電して、レジや電子レンジを動かして営業を継続されていました。自動車を発電機としてフル活用されていたのです。そのことを知って、今後の災害対策にEVこそ重要な役割を果たすのではないかと思いました。自然災害が頻発する中、企業のBCP(事業継続計画)も課題に上がってきていましたし、大規模停電によって自分たちが進めていたEV導入の必要性を再認識しました。

EVリースナンバーワンを目指すも、
待っていた散々な結果
EVの営業活動をスタートした直後はどのような感じでしたか?
K・M:CASEの流れに加え、BCP対策の重要性などから、このプロジェクトは社長自ら「EVリースでの業界ナンバーワンを目指す」とメッセージを発して企画が進みました。全社あげてのプロジェクトとなり、500人ほどの営業全員が販売に乗り出しました。 しかし当時の結果は、EVや電気に関する知識が乏しいこともあり、散々でした。最初の3ヶ月は、500人の営業社員が動いたにも関わらず、成約数はたったの10台だったのです。
K・R:私は営業活動をしなければならなかったわけですが、この企画が立ち上がったとき、正直どう提案すればいいのか、途方に暮れたことを覚えています。EVは高額ですし、車種も少ない。走行距離も短かった上に、都内で賃貸ビルに事務所を構えているところでは充電方法の問題もある。通常のガソリン車にとって変わるものではない状況で、どのようにお客さまにご案内するか悩みました。今思えば、クルマの価値の既成概念に捕らわれていたことが悩みの原因でした。その時には、K・MさんやS・Tさんなど営業企画部門の方にもだいぶ相談しました。

販売を好転させた
自動車メーカーに負けないEVの知識量
その苦境をどうやって乗り越えたのでしょうか?
K・M:最初の結果は散々でしたが、災害の多さや環境問題などの将来を考えたときに、当社としてEV化の必要性に対する考えは揺るぎませんでした。なんとかして、EVの必要性や価値をお客さまにお伝えしてご理解いただきたい、という強い思いがありました。
S・T:成約が伸びなかった問題の一つは、私たちの知識不足でした。それまで、ガソリン車やディーゼル車を販売してきて、そのあたりについては十分な知識を持っていたのですが、EVを提案するにはクルマの知識だけでなく電気の知識が足りなかった。そこが課題でした。
K・M:私が当時いた営業統括部は、営業部門の皆さんが商品・サービスの良さをよりよく伝えられるようにする、というのも大事な仕事で、そのためにも徹底的にEVと電気の知識を身に付けようとしました。書籍やネットに掲載されている情報もくまなく読み込んで、EVそれぞれのパーツを製造しているメーカーにまで電話して、いろいろなことを聞いていましたね。そして集めた情報を資料にまとめて毎週のように営業部門の皆さんに配っていきました。
当社でデモ用のEVを保有し、営業担当者に実際EVを体験してもらうなど、彼らが自信を持って提案できるように、考えられることはすべてやりました。
K・R:これまでのお客さまへの営業活動でも自動車メーカーさんに同行してもらうことはありましたが、EV提案では様々な利用シーンでのEVの活用方法や、建物からの充給電に関することなどは、私たちの方がメーカーさんより詳しい場合も多くありました。私たちがメーカーさんに代わってお客さまの質問に答えることもしばしばありました。
S・T:また、デモ用のEVを持っていたので、お客さまのところにEVを持っていって見てもらったり、助手席に同乗して体験してもらったりしました。そういった機会を積極的に作っていったことも、お客さまの理解を得られるきっかけになったと思います。

お客さまの必要性に応えるBCP対策
提案の切り口としてはどのようなものですか?
K・M:自然災害が頻発する中で、企業の社会に果たす役割は、さらに重要性を増している状況になってきています。その一つが企業そのものを存続させる力、そしてレジリエンスを高めることです。災害時、緊急時に通信手段や生命を維持するための最低限の電力を確保する手段の一つとして、BCP対策にEVを勧める方針を取りました。
2019年に、千葉県で台風が原因で起きた大規模停電の時には、お客さまの要請を受け、実際に当社で所有しているEVを現地に持ち込みました。そこで停電で困っていた福祉施設などにEVから電気を供給しました。給電先からは感謝され、その実績は私たちのお客さまや株主様からも非常に高い評価をいただきました。
今では、BCP対策やSDGsに関心の高いお客さまから「EV導入に関して話を聞きたい」「説明を受けたい」というご連絡をいただくまでになりましたね。
“お客さまのニーズに応えるだけ”ではなく、
“将来を見据えてお客さまのためになる提案”を
プロジェクトを通して感じたことはありますか?
K・M:以前は、お客さまのニーズにどう応えるかが営業活動のテーマと考えていました。しかし、このプロジェクトでは、お客さま自身も把握していない未来に先回りして、将来性のある、お客さまの気付いていない潜在ニーズに対する提案を行うなど、今まであまりできていなかったことを実践してきました。当時、EVがまだ広がっていないときに他に先駆けて情報を集めたり、何ができるのか必死に考えたり、いい経験になりました。また、結果として社会貢献につながるようなプロジェクトに携われて良かったと思っています。
S・T:K・Mさんが言うように、新しいチャレンジに参加できたことが良かったし、会社全体をあげてのことだったので、社内・社外を問わず大勢の人と協力して作り上げる喜びもありました。また、当社のチャレンジすることに対して応援するような社風、自由な雰囲気もプロジェクトを遂行するために良かったと思います。今、またどんどん新しいEVが出てきているので、それらに対応していくことが次の目標です。
K・R:車の性能や利便性以外のところでのアピールが必要とされた営業活動は、初めてで大変でしたが勉強になりました。EVを成約してもらった企業様からは「BCPにも使えるいいものを提案してもらった」と喜ばれることもありました。多くのメディアでEVが取り上げられ、SDGsやBCPが絡んで動きが活発になってきているのを感じます。成約件数も増えていますし、今までEV化を目指して経験してきたことが、これから力になっていくだろうと思います。
また、私が担当している医療や福祉の法人では、EV車は災害時に給電して明かりを灯したりすることはできても、今の車種では普段の高齢者の送り迎えや車椅子での利用が難しいといった点や、充電の問題があったりと、新しい課題が出てきています。EVリースが伸びてきているからこそ、新しく開発されるさまざまなEVや周辺サービスに目を向けて、今までの経験を生かしながら新たな課題解決にチャレンジしていきたいと考えています。