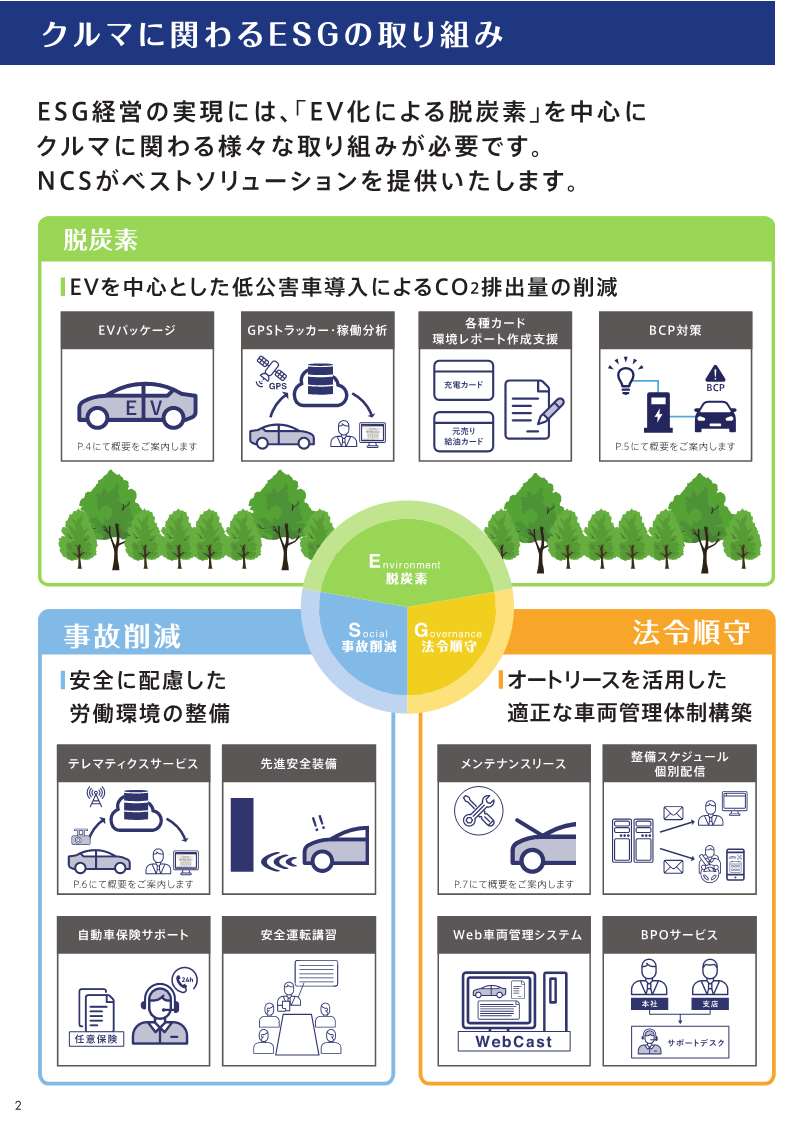- 課題/背景
-
-
建設・土木業は、他業種に比べてCO₂排出削減に貢献しづらい業種であることを自覚。環境に配慮した事業運営に率先して取り組む必要があった。
-
グループの「SDGs実行プログラム」を実現するために、独自に大蓉グループESG /SDGs実行委員会を立ち上げる。目標とするCO₂排出削減量を達成する上で、全営業車両のEV化が必須だった
-
- 選定理由
-
-
早くから「CO₂削減」の必要性を説き、企業が目指す姿やビジョンについて熱く語る代表者の理念に共感
-
既存のEV車両について乗り心地や課題などをヒアリングした上で、さまざまなメーカーの車両情報を提供してくれる点
-
- 導入の効果
-
-
SDGs実行プログラムが目指すCO₂排出削減量の目標値をクリア。定期的に走行距離や目的地までのルートを社内で共有し、EVの運用方法を改善
-
EVは外回りの営業を行う社員に貸与。EVの快適性やCO₂削減効果を実感してもらうことで、社員の意識改革に貢献
-
大蓉ホールディングスは、大蓉工業・大煌工業・大煌モーターズ・日本ソーラー発電・オフィステクノロジーなどのグループ会社で構成される企業グループで、建設・土木事業・運送事業・自動車整備事業・農業・紫外線殺菌事業・ホテル事業・レストラン事業・物販事業の運営をグループ各社にて展開しています。2024年には創業30周年を迎え、企業理念である「我々の周りに関わる全ての人々が幸せになる事を目的に日々活動し続ける100年続く企業を目指す」を推進しています。
課題/背景
100年先の地球環境を守るために、
環境に配慮した事業運営に取り組む

写真左から
大煌工業株式会社 代表取締役社長 山下 将弘氏
大蓉工業株式会社 代表取締役社長 見城 雅也氏
大蓉工業株式会社 取締役副社長 大草 裕之氏
私たちのコア事業は、建設・土木事業です。スーパーゼネコン・ゼネコンと呼ばれる大手建設会社をクライアントに持ち、大型建築工事や大型公共工事の土木・掘削に携わっています。ひとことで「建設・土木事業」といっても建設現場における建築工程はさまざまで、工事・運搬・処分・造成などのさまざまな業務が発生します。上流から下流に至るまで、複数の建設・土木業者がいるなかで、私たちはそれぞれの専門分野に特化し、一貫した責任施工を通じてワンストップソリューションを提供しています。
グループシナジーがもたらすメリットは、お客さまに対してだけではありません。建設・土木事業をメインとする私たちが農業を展開していることに違和感を持たれる方もいると思いますが、私たちが育てているのは熱中症予防に効果的といわれる「トマト」。建設・土木工事は屋外での作業が多く、夏場は熱中症の発生リスクが高まります。そこで、自社で栽培したトマトを使ってジュースを作り、作業員や社員に提供。2024年は熱中症の事例をゼロに抑えることができました。炎天下では熱中症対策を講じるために工期の遅れが懸念されますが、できる限り作業を止めないため、お客さまにとってもメリットのある取り組みだと考えています。

(写真)太陽の恵みと自然の恩恵を受けた『タイヨウノトマト~べにすずめ~』。ゼロエミッション栽培を実践し、脱炭素への取り組みを実践
ホテル事業・レストラン事業・物販事業を展開するのも、社員の健康や生活を守るため。2011年に発生した東日本大震災においては、福島県内の市町村の除染作業で生じた土壌の運搬を行いましたが、200万立方メートルもの土を中間貯蔵施設まで運ぶ作業員のために、宿泊場所としてホテルを開業。さらに、レストランやコンビニも設置しました。土木・掘削から始まって30年間、お客さまだけでなく、社員も含めて幸せになることを目的に事業を拡大させています。
建設業は都市や地域経済を支える重要な産業のひとつ。総合生活産業としての側面を持ちながらも、建設に伴うエネルギー消費は大きく、そこから排出されるCO₂も莫大になります。自然環境に影響を与えかねない私たちだからこそ、環境に配慮した事業運営に率先して取り組んでいかなければならない。そんな想いから、2021年にSDGs実行プログラムを策定しました。当社の企業理念に基づき、100年先の地球環境を守るために、持続可能な社会の実現に向けて、社用車のEV化を含むさまざまな取り組みをスタートさせています。

(写真左)東京ガールズコレクションがデザインしたオリジナルの「サスティナブル作業着」。着古した作業着は、回収後にリサイクルされて製品にアップサイクルする。作業着のイメージを一新したスタイリッシュかつ高機能なデザインは社員だけでなく、お客さまからの評判も良好。
(写真中央)建設機械の使用燃料には、環境負荷の少ない天然ガス由来の軽油代替燃料・GTL燃料を積極的に使用。軽油と比べてCO₂排出量を8.5%削減するとともに、車両汚れの原因となる煤(すす)が出ないため、建設機械から排出される有毒物質の低減効果が期待でき、環境負荷の影響を抑制。
(写真右)自社所有の太陽光発電所がある千葉県鴨川市の山林をナラ枯れの被害から守るために、ヤマザクラを毎年1,000本ずつ植林していくプロジェクトを開始。これまでに3,000本のヤマザクラの植林を行った。植林活動によるCO₂吸収量を見える化し、持続可能な活動として推進する。
SDGs実行プログラムのプロセスや、目標に対する進捗状況を確認するのは、各職種の代表者で構成される大蓉グループESG/SDGs実行委員会です。各職種の代表者を実行委員に任命したのは、社員一人ひとりに、自分たちの行動が環境保全やCO₂削減につながっていることを肌で感じてもらうため。SDGsは社会的に解決しなければならない命題であり、代表がトップダウンで進めれば良いというものではありません。しかしながら、環境教育になじみのある若手社員と、そうでないベテラン社員の間にはSDGsの受け止め方に温度差がありますし、手間や時間を要する取り組みには現場が消極的になる恐れもあります。社員が当事者として会議に参加すれば、取り組みの成果がCO₂排出量や削減量などの数値に現れるため、結果的に持続可能な活動として実行委員会を推進できるのです。
各職種の代表者には、会議の内容を各社・各職種に共有する役割がありますが、基本的には社員主導で取り組みや活動のアイディアを話し合ってもらい、これまでもペットボトルのキャップ回収による子どもワクチン支援、使用済み切手を集めて国際支援につなげるといった取り組みが生まれています。
選定理由
NCSとの出会いがきっかけで、SDGs達成へ大きくシフト。
熱い想いに心を動かされてEVを導入
当グループは、2027年度以降社用車をすべてEV車両へ変更することを目標に掲げ、順次EVを導入しています。2019年に13台の日産リーフを導入し、2024年には新たにBYD ドルフィン ロングレンジを2台導入しました。さらに、11月にはフォロフライ社製EV F1 VAN1台の納車と、急速充電器・普通充電器の設置を控えています。
SDGs実行プログラムでは、さまざまな項目でCO₂の削減値を設定しており、その目標を達成するために、当初からEV車両の導入を計画していました。というのも、従来のガソリン車から排出されるCO₂を削減できれば、その分だけCO₂排出量抑制に貢献できるからです。そこで、既存車両のリースで取引のあるNCSへ相談し、EV車両の情報提供を受けながら、SDGs実行プログラムに基づいたEV導入計画を立てました。
NCSを選んだ理由は、当時のNCS社長であった野上誠さんから熱意をもって強く推奨されたこと。複数のカーリース会社からEV導入のご提案をいただきましたが、正直言うと車両や金利なども含めて提案内容に大きな違いはありませんでした。そんななかでも、NCSは代表者自らが当社まで足を運び、脱炭素をめぐる企業の動向やCO₂削減の意味、有事の際に電源供給のもとになる有難さを熱く語るその姿に心を打たれました。EVの経済性や利便性をアピールする以上に、「企業が目指す姿やビジョンはこうあるべきだ」と語る代表者の理念に共感し、その場で13台契約したことを覚えています。そこから社内がSDGs達成に向けて意識をシフトし、大蓉グループESG/SDGs実行委員会の立ち上げにつながりました。当社が大きく変わるきっかけを与えてくれたNCSには感謝しています。
2019年にEVを導入した後も、NCSとは継続的なお付き合いを続けながら、EVの乗り心地や運用上の課題などをヒアリングいただき、さまざまなメーカーの車両情報をタイムリーに提供していただいています。既存のEV車両は航続距離や充電頻度の点で課題を抱えていましたが、航続距離の長いEVをご提案いただき、ガソリン車と近い水準の航続距離や充電頻度、コスト面でも申し分がないと納得し、2024年に2台導入しています。
導入の効果
「EV導入」を持続可能な取り組みにしていくために。
社員の乗り心地や使い勝手もヒアリング

EV導入の効果は、CO₂削減と社員の意識改革です。大蓉グループESG/SDGs実行委員会でCO₂排出削減量を設定する際に、NCSとの関わりのなかで、ガソリン車のリース契約が満了となるタイミングでEVに切り替えることを決めました。導入される年度と台数をあらかじめ計画に入れているため、計画通りに進められれば、2027年度には社用車から排出されるCO₂排出量はゼロになります。
当社にはさまざまな年齢・職種・階層の社員が在籍しています。特に経営層と現場で働く若手社員では年齢や経験が大きく異なり、SDGsに対する意識の差は顕著です。この差を埋めるには、経営層や管理職の意識改革が必要になりますし、時には社員が理解するまで何度もコミュニケーションを重ねていく必要があるでしょう。その点、普段の通勤や外回りで使う社用車がEVになれば、「持続可能な環境の実現に自分たちも貢献している」という実感を肌で感じることができ、社員間の意識の差を埋めるのに役立つと考えています。経営層としては、これまで使っていたガソリン車のCO₂排出量と比較するなどして、社員の貢献を目に見えるような形で表現することが必要でしょう。
EVを導入する目的はあくまでも「CO₂削減」ですが、持続可能な取り組みとして実施していくのであれば、乗り心地や使い勝手も重要な要素です。EVに乗車している社員に話を聞くと、ガソリン車よりも静粛性と加速性に優れており、またアイドリングストップしてもエアコンが止まらないため、夏場でも快適に過ごせているようです。また、BYD ドルフィン ロングレンジに乗る社員からは、航続距離や充電頻度に関する不安解消はもちろん、充実した機能や装備が採用されているので、満足しているとの声もあがっています。

(写真)新たに導入したBYD社・ドルフィン ロングレンジ。大型のディスプレー(インストゥルメントパネル)は、見やすく操作しやすいとのこと。
(写真)ゆとりある室内スペースで、収納力も抜群。また、座席は車体価格以上の高級感があり、長距離・長時間運転していても疲れにくく、社員に好評。
最近納車されたBYD ドルフィン ロングレンジは、個性的なツートンカラーのデザインです。ひときわ目を引くデザインということもあり、お客さまから「EVに乗り替えたの?」「どこのメーカーのEV?」と声をかけていただく機会が増えました。世間話のネタとしてはもちろん、当グループの活動をアピールするきっかけにもなっています。
今後の展望
日本で唯一の土木・掘削会社を目指して。
水素製造プラントの建設計画を推進
私たちと同じ建設・土木事業でEV導入を検討している企業も多いと思いますが、なかには「EVを導入したからといって、何も変わらない」と考える方も多いものです。確かに「社用車をEVに変える」という考え方をしていては何も変わらないでしょう。大切なのは、組織の目的とアクションにひもづく効果を見える化すること。当グループの場合は、SDGs実行プログラムを体系的に整理し、普段の業務(外回り)との接点を持たせながら、EVの有用性を数値で表現しています。企業のビジョンや目標を具体化し、それに向けたアクションを考えるという順序で考えなければ、EVを導入したとしても一過性のもので終わってしまうでしょう。
独自に進める水素プラント事業に伴い、現在所有する大型土砂運搬車両をすべて燃料電池車(FCV)へ変更することを計画しています。FCVは水素と酸素の化学反応によって発生する電気を使って走る車両で、走行中にCO₂を排出しないことから、脱炭素社会に貢献する自動車として期待されています。大型車のFCV量産化には課題も多く、導入には時間を要するでしょう。ただし、大型車のFCVが商品化されたあかつきには、構想中の水素製造プラントを稼働させ、自社製造のグリーン水素で大型車両を動かす、つまりCO₂を一切排出しない日本で唯一の土木・掘削会社になると確信しています。NCSには継続して車両に関する情報をご提供いただきながらも、当グループが推進するSDGs実行プログラム実現に向けて伴走していただければと思います。
当グループの2024年のキャッチフレーズは「確かな土木・掘削技術と運送技術に裏付けされたコンプライアンスの実現をした上で、サスティナブルな新しい日本基準を作る」です。土木・掘削の専門業者として、私たちにできることはまだまだあります。常に環境にやさしい技術と業務プロセスを追求し、環境負荷の低減に努めながら、新しい土木掘削技術と運搬技術で日本の常識を作ろうと、すべての組織・職場で社員一人ひとりが行動を起こしています。大蓉ホールディングスのこれからにご期待ください。